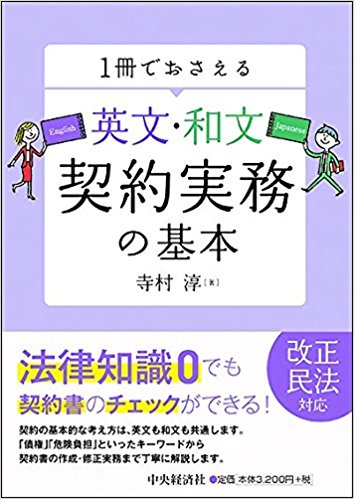ライセンス契約の特徴と作成のポイント4−寺村総合法務事務所
Email: legal(at)eibun-keiyaku.net
〒190-0022 東京都立川市錦町6-4-10-306
代表:寺村 淳(東京大学法学部卒、日本製鉄勤務17年)
ソフトウェアライセンス契約の説明−4COMPANY
トップページ>目次>ソフトウェアライセンス契約3>ソフトウェアライセンス契約4>ソフトウェアライセンス契約5
3.ソフトウェア・ライセンス契約(サブライセンス権付き)の構成とポイント−4
- 保証条項(Warranty)
ここでの保証は、ライセンサーの提供する本ソフトウェアおよびそれに含まれるプログラムや関連資料に関する権利が、ライセンサーに正当に帰属することについての保証が中心です。
ここがはっきりしないと、ライセンシーとしては、自らが許諾された権利の行使に問題がないかどうか確信を持てない訳ですから、ライセンシーとしては必ず保証してもらう必要があります。
また、販売契約的な要素として「瑕疵担保」責任についても触れておくことが多いようです。
通常ソフトウェアのライセンス契約では、ライセンサーから「仕入れる」のではなく、1本もらってそれをライセンシーが複製した上でサブライセンスしていくことになります。
しかし、最初のその1本について、隠れた瑕疵=不良・バグなどがあった場合、ライセンサーに完全なものを出させることを求めるのは、当然必要な行為となります。
そして、もしライセンサーが完全なソフトウェアを最後まで提供できない事態であれば、それは、このライセンス契約という枠組みが維持できない事態になりますので、契約解除、損害賠償へと移って行ってしまうことになります。また、ミニマム・ロイヤルティ等については返金をどうするか、という問題になっていきます。
契約が中途で解約されても、イニシャルで支払ったダウン・ペイメントについては、一切返金しない、とする場合が普通でしょうが、上記のような根本的にソフトウェア製品に問題があってビジネスの展開に支障があったような場合は、それら支払った額の払い戻しを受けることができるとすべきでしょう。
- 侵害条項(Infringement)
ライセンサーの本ソフトウェアに関する権利(知的財産権)を守ることは、ライセンサーのみならずライセンシーにとっても利益になります。
そこで、この条項では、本ソフトウェアに関する知的財産権等に関して第三者と紛争が生じたり、第三者が違法な使用を行っていたような場合には、互いに通知しあい、その被害を最小限に食い止めていきましょう、という事を規定しています。
契約条項上の体裁は、ソフトウェアや技術の開発者であり保有者であるライセンサーが、原則として紛争に関する全責任を負う旨が規定された上で、ライセンシーの協力義務が書かれることが多いようです。
ただ、ライセンサーとしては、知的財産権紛争が一体誰の責任で発生したか、ということを明確にしておき、何でもかんでも自分の責任として背負いこまないことが肝要です。
ライセンシーが改良したり他のものと組み合わせたことに起因して、知的財産権紛争が発生する場合もあります。特に「特許」については、単体では特許侵害とならずとも、他の技術や条件と組み合わせると、第三者の特許に抵触する可能性が生じます。
従って、ライセンサーとしては、どれだけ自分の責任を合理的に限定できるかがポイントとなります。
- 宣伝条項(Advertisement)
ライセンサーとしてはライセンシーにどんどん宣伝してもらって、本ソフトウェアの販売拡大、ロイヤルティ収入の増大を目指したいわけです。
その宣伝広告の費用は、ライセンシーが負担することが普通でしょう。
ただ、ライセンサーが本ソフトウェアの他国版のカタログを提供したり、価格表やサービスレベル(保守の範囲)に関するカタログをライセンシーに提供することもあると思います。その場合費用負担者を明確化しておくことが必要です。
また、ライセンシーの広告宣伝の「やり方」「態様」といったものについて、ライセンサーがどこまで口を挟めるか、についても議論の余地があります。
ライセンサーは、自社のイメージを損なってほしくないため、ライセンシーの作成するすべてのカタログ、パンフ、ウェブサイトなどに、事前承認や事後承認プラス改変要求権を求めてくることが多くみられます。
単に、「ライセンサーの良い価値あるイメージを損なう態様で広告宣伝を行わないよう努める」という訓示規定にとどめるか、あるいは、ライセンサーの事前承諾、果ては差止権や事後監査権までをも認めるのか、交渉力がものをいうところです。
- 商標条項(Trademarks)
前条の宣伝条項に深く関係する条項ですが、ライセンシーが本ソフトウェアに関する宣伝広告を行う場合に、パンフレット等にライセンサーの商標、ロゴ、ライセンサーの名称を使用することを義務付けるかどうか、という規定です。
ライセンサーの作成したソフトウェアをあまり変更せずに再使用許諾していく場合と、ライセンシーがローカライズして販売していく場合、あるいはネット上のASPとして提供していく場合、などなどの形態の違いもあり、ライセンサーの商標等の使用を認めない場合、逆に積極的な使用を義務付ける場合、などがあります。
名称を付すことは自社名称の普及に役立ちますが、ライセンシーの信用力や能力、商売の成り行きによっては、自社イメージを逆に損なう可能性もあります。
その点を見極めたうえで、例えばパンフレット等への掲載は事前承認制にする、とか、何時でも差止ができる旨を規定したりして、ライセンサーの信用の保護を図る規定がおかれることが多いと思われます。
- 秘密保持条項(Non-Disclosure)
守秘義務に関する条項です。
ソフトウェア・ライセンス契約は、継続的関係を規律する契約であると共に、非常に各当事者の内部ノウハウの開示がなされやすい形態の契約だと言えるでしょう。
複製/改変をして再使用許諾をするという場合に、複製/改変するために、ライセンサーの技術情報やオブジェクトコード又はソースコード情報などを必要とする場合がほとんどでしょう。
そのようなライセンサーの秘密情報は、ライセンサーの企業としての生命線である場合も多いことから、非常にシビアな守秘義務がライセンシーに課せられる場合もあります。
その上で、開示範囲(秘密情報の定義)と、例外条項の範囲、守秘期間を定めていくことになります。
例外についてですが、独自開発の部分をどの程度認めるかについてなども重要で、前述の知的財産権の帰属の問題と同様、その証明が問題となります。
例外に関して、もうひとつ、裁判所・官公署からの法に基づく開示要求の場合について問題があります。
官公署からの開示要求の場合、情報そのものが公知になっているわけではありません。
官公署等の命令があったからといって、開示される情報の秘密性は何ら失われておらず、法に従いつつも、できるだけその開示範囲を狭めることが情報の開示者の利益となります。
従って、その開示範囲を最小限にするために、事前通知義務を相手方に課し、情報開示を避けるための手段があれば取れるようにすること、あるいはインカメラ手続き(裁判手続きの中で公開せず裁判官だけに証拠を開示する方式)などを最大限に利用する義務などを課すことが必要となります。
期間については、前記の通り、ソフトウェアに関する情報はノウハウであり厳格に秘密に保持されることが要求されますが、その半面、速やかに「陳腐化」する情報であるとも言われており、契約終了後3年間だけ義務を負う、という短期の義務消滅を定める場合も多いようです。
もう一つのポイントは、再使用許諾権付きである場合に、再使用許諾を行うリセラーに対して、ライセンシーが開示できる情報の範囲についての定めでしょう。
なかなか難しいところがあり、結局ライセンシーに一切の責めを負わせることになってしまうことが多いと思いますが、情報を本当にリセラーに出す必要があるのかなども点検してみることも肝要でしょう。
さらに、ライセンス契約が終了した場合の措置について、しっかり考えておくことが必要です。
ライセンス契約が何らかの事情で解除または終了してしまった場合でも、本ソフトウェアを使用しているエンドユーザーは残るわけですから、そのひとたちの権利がどうなるか、という問題があります。
秘密情報に関して言えば、契約終了後においても、エンドユーザーの保守サポートをする関係上必要となる最小限の技術情報の保有、使用というものは、ライセンシーに認められるべきものです。
ただ、契約解消後のエンドユーザーサポートをライセンサーないし他の会社が引き継ぐという場合は別です。
バナースペース
寺村総合法務事務所
https://
www.keiyaku-sakusei.net
〒190-0022
立川市錦町6-4-10-306
事務所開設:2003年
代表 寺村 淳
東京大学法学部1985年卒
日本製鉄法務等企業17年
早稲田大学オープンカレッジ講師
行政書士/宅建主任有資格
Email:legal(at)eibun-keiyaku.net
(at)を@にして下さい
TEL042-529-3660
はじめての英文契約書の読み方
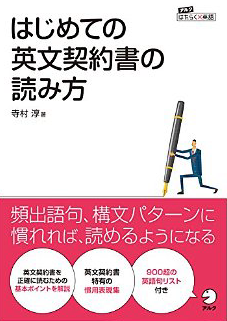
はじめての英文契約書の読み方
(電子版)
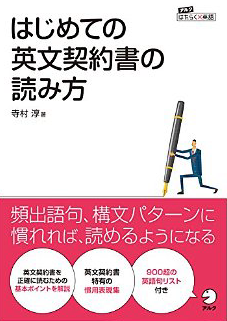
1冊でおさえる-英文・和文
契約実務の基本